私たちが学んでいる現代英語は、突然完成したものではありません。
その背後には、長い時間をかけて形づくられてきた歴史があります。
なかでも近世英語(初期近代英語)の時代は、英語が中世的な言語から脱皮し、現在の姿へと決定的に近づいた転換点でした。
この時代、英語は語彙・文法・文体のすべてにおいて大きな変化を経験します。
ルネッサンスによって抽象的で知的な語彙が流入し、シェイクスピアによって表現の可能性が押し広げられ、欽定訳聖書によって英語の文章のリズムと型が社会に定着しました。
その結果、英語は日常の言葉であると同時に、思想や感情を精緻に表現できる言語へと成長していきます。
この記事では、近世英語とは何かという基本的な位置づけから出発し、語彙と表現、文体の変化をたどりながら、現代英語の原型がどのようにして形づくられたのかを見ていきます。
英語が「なぜ今のような姿になったのか」を理解することは、英語学習そのものを深める手がかりにもなるはずです。
近世英語とは何か
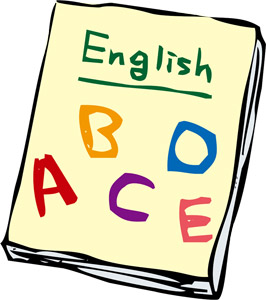
近世英語(初期近代英語)とは、英語の歴史において中英語の時代の後に続く段階で、おおよそ1500年頃から1700年頃までの英語を指します。
この時代は、現代英語へと直接つながる基盤が形づくられた非常に重要な時期です。中世的な言語から近代的な言語へと英語が大きく転換した、いわば「過渡期」でありながら、同時に「完成期」でもあったと言えます。
中英語との最大の違いは、英語がもはや地域ごとに大きく分断された言語ではなくなった点にあります。
中英語の時代には、方言差が激しく、同じ英語でありながら文章の理解が困難な場合も少なくありませんでした。
しかし近世英語の時代に入ると、印刷技術の普及や政治・文化の集中化によって、ロンドンを中心とする英語が事実上の標準として広まり始めます。
その結果、語彙や文法、綴りのばらつきは次第に収束していきました。
また、文法の面でも大きな変化が見られます。
中英語に残っていた屈折語尾はさらに簡略化され、語順によって意味を表すという、現代英語に近い構造が定着しました。
主語―動詞―目的語(SVO)の基本語順が安定し、助動詞を用いた表現も体系化されていきます。
これにより、英語はより論理的で、明確な言語へと変わっていきました。
語彙の面では、近世英語は爆発的な拡張を経験します。
後で触れるルネッサンスの影響によって、ラテン語やギリシア語に由来する語彙が大量に流入し、英語は日常的な言語であると同時に、学問や思想を表現できる言語へと変貌していきます。
この語彙の二重構造は、現代英語の特徴の一つでもあります。
このように近世英語の時代は、発音や綴りに歴史的な揺れを残しつつも、文法や語彙、文体の基本枠組みがほぼ出そろった時代です。
その意味で、近世英語は「現代英語の原型がほぼ完成した時代」と位置づけることができます。
私たちが現在使っている英語は、この時代に形成された骨格の上に成り立っているのです。
ルネッサンスと英語
近世英語の語彙を決定的に変えた要因の一つが、ルネッサンスの影響です。
ルネッサンスは古代ギリシア・ローマ文化の再評価を特徴とする知的運動で、イングランドにも学問・教育・思想の刷新をもたらしました。
この動きの中で、英語にはラテン語やギリシア語を源とする語彙が大量に流入します。これが、英語が一気に「知的な言語」へと変貌した瞬間でした。
それまでの英語は、日常生活や具体的な行為を表すには十分な言語でしたが、哲学や科学、政治、神学といった抽象的な概念を表現するには語彙が不足していました。
そこで学者や知識人たちは、既存の英語ではなく、権威あるラテン語やギリシア語の語を取り入れることで、新しい概念を表そうとしました。
その結果、英語には抽象語や学術語が急増することになります。
この時代に流入した語彙は、現代英語にもはっきりと痕跡を残しています。
たとえば -tion は行為や結果を名詞化する語尾で、nation や education、information などに見られます。
-ity は性質や状態を表し、authority や possibility、identity といった語を生み出しました。
さらに -ism は思想や主義を表す語尾で、humanism や capitalism、nationalism などに受け継がれています。
これらはいずれも、ラテン語・ギリシア語由来の知的語彙の典型です。
英語学習者が「英語の語彙は難しい」と感じる理由の多くは、この二重構造にあります。
日常的な場面ではゲルマン系の短い語が使われる一方、抽象的・学術的な文脈ではラテン語・ギリシア語由来の長い語が用いられます。
help と assist、ask と inquire のように、意味は近くても語感や使用場面が異なる語の対立は、まさにこの時代に形成されたものです。
ルネッサンスを通じて、英語は単なる話し言葉から、思考や議論、学問を担う言語へと飛躍しました。
近世英語のこの変化によって、英語は感情や行動だけでなく、抽象的な理念や複雑な思想をも表現できる言語となります。
現代英語がもつ語彙の豊かさと知的な表現力は、この時代の大胆な借用と拡張の上に築かれているのです。
シェイクスピアの影響力
近世英語を語るうえで、シェイクスピアの存在は欠かすことができません。
彼は単なる劇作家や詩人ではなく、英語そのものの可能性を大きく押し広げた人物でした。
シェイクスピアの作品が書かれた時代、英語はまだ発展途上にあり、語彙や表現の使い方には大きな自由度がありました。彼はその余白を最大限に活かし、英語表現を飛躍的に豊かにしたのです。
まず注目すべきなのが、新語の創造です。
シェイクスピアは既存の語を名詞から動詞へ転用したり、接頭辞や接尾辞を組み合わせたりすることで、多くの新しい語や用法を生み出しました。
lonely や fashionable、critic など、現在ではごく当たり前に使われている語も、シェイクスピアの作品を通じて広まったとされています。
彼は英語を「使いながら作る」ことを恐れなかった作家でした。
次に重要なのが、日常語と文学語の橋渡しを行った点です。
それまでの文学は、ラテン語的で格式ばった表現に寄りがちでしたが、シェイクスピアは市場や家庭で話されていた生きた英語を積極的に作品に取り入れました。
その一方で、比喩や修辞を駆使した高度な表現も用い、日常的な語彙を芸術の水準へと引き上げています。
この融合こそが、彼の英語が独特の力をもつ理由です。
表現の柔軟性という点でも、シェイクスピアは突出しています。
語順を大胆に入れ替えたり、一つの語に複数の意味を重ねたりすることで、登場人物の感情や心理を生き生きと描き出しました。
直喩や隠喩、誇張や反語といった表現技法は、単なる装飾ではなく、英語の持つ表現力そのものを試す実験でもありました。
そのため、文法的には理解できても意味をつかみにくい箇所が生まれやすく、これが「シェイクスピア英語は難しい」と感じられる理由の一つです。
しかし同時に、シェイクスピアの英語は驚くほど現代的でもあります。
彼の生み出した言い回しや表現の多くは、形を変えながらも現代英語の中に生き続けています。
つまり、シェイクスピアの英語は古い過去の遺物ではなく、今の英語につながる流れの中に確かに存在しているのです。
欽定訳聖書の影響力
シェイクスピアと並び、近世英語の文体を決定づけた存在として、欽定訳聖書の影響はきわめて大きいものがあります。
1611年に刊行された欽定訳聖書は、王の権威のもとで編まれた公式の英語聖書であり、宗教書であると同時に、英語史における画期的な文学作品でもありました。
この翻訳は、英語の文章がどのように書かれるべきかという基準を、多くの人々に示す役割を果たしました。
欽定訳聖書の最大の特徴の一つは、標準的な文体を確立した点にあります。
中英語から近世英語への移行期には、綴りや語法、文の組み立て方にまだ揺れが残っていました。
しかし欽定訳聖書は、広く読まれ、朗読され、暗唱されることによって、自然と模範となる英語を社会に浸透させていきます。
その結果、英語の文体は一定の安定性と統一感を獲得しました。
また、欽定訳聖書は平行構文を多用し、独特のリズム感をもつ文章を特徴としています。
同じ構文や語順を繰り返すことで意味を強調し、耳に残る表現を生み出しました。
このリズムは、もともとヘブライ語やギリシア語の原文がもっていた構造を意識したものですが、それが英語として非常に美しく、力強い形で再構成されています。
英語の文章が朗読に適していると感じられるのは、この伝統に負うところが大きいと言えます。
さらに、現代英語で日常的に使われている多くの言い回しが、欽定訳聖書を源泉としています。
慣用表現や比喩的な言い回しがこの翻訳を通じて定着し、宗教的な文脈を超えて一般語として広まりました。
英語にどこか荘重で格調高い響きが感じられる場面があるのは、聖書文体の影響が無意識のうちに受け継がれているからです。
欽定訳聖書は単に内容を伝えるための翻訳ではなく、英語の文章そのものを形づくる役割を果たしました。
英語学習者にとっても、この影響を理解することは重要です。
英語の文章に流れるリズムや、意味を強調する構文の使い方を意識すると、なぜ英語が「聖書っぽい響き」をもつのかが見えてきます。
欽定訳聖書は、現代英語のリズム感のルーツとして、今なお生き続けているのです。
そして近代英語へ
近世英語の時代が終わる頃、英語はすでに言語としての基本構造をほぼ完成させていました。
語順を中心とする文法体系は安定し、助動詞や時制の使い方も現代英語と大きく変わらない形に定着しています。
以後の英語史において、文法が根本的に書き換えられることはほとんどなくなりました。
この点で、近世英語は一つの到達点だったと言えます。
一方で、語彙の面ではまったく異なる展開が始まります。
近代に入ると、大英帝国の拡大とともに英語は世界各地へと広がり、各地域の言語や文化と接触するようになります。
その過程で、英語は外来語を大量に取り込みながら成長していきました。アジア、アフリカ、アメリカ大陸などから流入した語彙は、英語の表現領域をさらに押し広げることになります。
この時代の変化を特徴づけるのは、英語の役割そのものが変わった点です。
それまでの英語は、主にイングランドの人々が用いる「母語」でした。しかし近代以降、英語は異なる言語背景をもつ人々の間で使われる共通語、すなわち「世界語」へと姿を変えていきます。
英語は特定の民族や地域に属する言語ではなく、実用的なコミュニケーションの道具として用いられるようになったのです。
このことは、現代英語の多様性とも深く関係しています。
発音や語彙、表現の使い方に地域差や揺れが存在するのは、英語が世界中で使われ、各地の現実に適応してきた結果です。
文法の骨格が共通である一方、語彙や表現に幅があるという特徴は、まさに近代以降の歴史が生み出したものです。
次回は、この近代英語の時代をさらに詳しく見ながら、英語がどのようにしてグローバルな言語として定着していったのかを見ていきます。
前回(中英語)の記事

次回(近代英語)の記事


